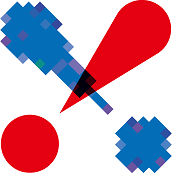ネットで
見る

-
[講義]チャンネル会員無料

-
[講評]一般無料
〈ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾〉の講義を生中継します。「講義」部分の視聴はゲンロン完全中継チャンネルの会員の方限定となります。
「講評」部分の中継は一般の方でもご視聴いただけます。「講評」部分については、タイムシフトを公開しません。あらかじめご了承ください。
■
【課題】
批評再生塾ではこれまでも3年間にわたって、映画(映像)批評をめぐる課題を、さまざまな視角から出してきました。1年目は映画の「定義」、2年目は映画の「記述」、3年目は映画の「受容」をめぐる課題だったといっていいでしょう。そこで今年度は、映画をめぐる「歴史感覚」を、批評家として鍛える課題を出そうと思います。
今年度の課題は以下です。
「今年(2018年)の映画をめぐる状況をなんらかの軸にして、映画史の新しい見取り図を作ってください」
【いくつかの補足】
・ここでいう「映画」「映画史」とは狭義の映画に限らず、あなたが作る「新しい映画史」に関係すると考えるならば、どのような作品/表現/オブジェクト/現象を対象にしてもかまいません。
・「映画史」の範囲ですが、最短でも平成年間(1989〜2019)を視野に入れてください。
・2018年公開の作品を含め、過去から現在まで、「新たな映画史」にとって指標となるような作品/表現/オブジェクト/現象などを必ず出してください。
・分量は特にこちらからは指定しません。
この批評再生塾でも何度か話していますが、ぼくは批評の役割とは、「パースペクティヴの組み替え」だと考えています。ぼくたちはつねに、作品であれ作家であれ社会現象であれ、既存の社会や文化に沈殿しているお仕着せの見取り図や方程式にしたがってそれらに接している。しかし、批評的ないとなみとは、人類がこれまでに蓄積してきた多種多様な知見を縦横に参照しながら、そうしたお仕着せのモノサシではない、世界とぼくたちとの、新たな距離感や布置を作り上げていく作業です。そこに批評をやること、また読むことの、ワクワクするような創造性があります。
さて、この批評が創出するパースペクティヴとは、当然、さまざまなジャンルや表現の歴史にこそ、当てはまるでしょう。しかも、もともと映画というジャンルは、こうした映画史的記憶の身体化や規範化を他のジャンルよりも強固に求める批評スタイルが、一定の期間、強い知的影響力を担っていたことがありました。いうまでもなく、「シネフィル」という存在に理念的に仮託されるような批評スタイルがそれです。そして、文化全体の教養主義の没落とともに、21世紀に入るころには、そうしたタイプの映画との接しかたもいつしかリアルなものではなくなってしまった。
ところが、興味深いのは、近年になって、かつてシネフィルが体現していた映画体験と歴史性との強固なかかわりかたが、新たなリアリティとスタイルをもって復活しているような気がすることです。たとえば、今年相次いで刊行された『『ハッピーアワー』論』や『オーバー・ザ・シネマ』といった映画論の話題書は揃ってこのテーマを意識していますし、手前味噌ながら、今年終了した『ゲンロンβ』でのぼくの連載もある意味で同じ問題を扱っていました。『オーバー・ザ・シネマ』でも参照された菊地成孔氏の名言を出せば、いままた、「シネフィルがもう一回オッケーになりつつある」わけです。
そしてそこには、『『ハッピーアワー』論』の三浦哲哉氏が出す、フランスの映画批評家アンドレ・バザンがかつてもちだしたという「幼形成熟」(ネオテニー)の例もかかわってくるでしょう。幼形成熟とは、ウーパールーパーが有名ですが、生き物の個体のうち、成体に成熟しても幼体のときの性質がポテンシャルとして保持されている状態を指します。バザンはサイレントからトーキーへ、そしてネオレオリスモへという、戦後の新たな映画の状況を見ながら、映画とは一見、すでに完成されきった芸術に思えるが、じつはまだまだわれわれの知らないポテンシャルを孕みもった幼形成熟の状態にすぎないのではないかと考えました。そして、三浦氏のいうとおり、このバザンの歴史感覚は、「ポストNetflix」時代のいま、映画についてますますリアルなものになっていると思えます。
たとえば、ぼくはいま、それこそNetflixでほとんど観たことがなかった『男はつらいよ』シリーズをビンジウォッチ(一気見)することにハマっているのですが(笑)、ストリーミング配信で『男はつらいよ』をつぎからつぎに海外ドラマのように観ることを可能にした今日のメディア的な慣習は、かつて昭和の時代に盆休みと正月の劇場興行のリズムで観ていた当時の観客たちとはまったく異なる文脈を、ぼくたちの映画をめぐる歴史感覚にもたらすでしょうし、そのことによって、それまでされてきた評価とは全然違ったかたちで、作品を新たな映画史的パースペクティヴのもとに位置づけることができるようになるでしょう。そして、そうした状況の到来には、濱口竜介監督など、新たな映画作家の登場が深く関係してもいるわけです。
というわけで、今回はみなさんに、2018年の現在から見た新たな映画史の見取り図を大胆に構想してもらおうと思っています。もちろん、今回の課題をこなすために、オーソドックスな映画史の知識があるに越したことはないですが、逆にいえば、歴史とは物語なので、仮にそうした知識がなくとも、いかにも説得力のあるオーソドックスな映画史の姿を「捏造」できることも、批評家としての重要な才覚のひとつでしょう。
■
<運営による追記:今回ゲスト講師から文字数制限はありませんので、批評再生塾の基準である「2000字~8000字」を選考対象とします。>
当日のtweetのまとめはこちら!
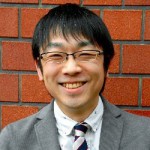
渡邉大輔 Daisuke Watanabe
1982年生まれ。映画史研究者・批評家。跡見学園女子大学文学部准教授。専門は日本映画史・映像文化論・メディア論。映画評論、映像メディア論を中心に、文芸評論、ミステリ評論などの分野で活動を展開。著書に『イメージの進行形』(2012年)、『明るい映画、暗い映画』(2021年)。共著に『リメイク映画の創造力』(2017年)、『スクリーン・スタディーズ』(2019年)など多数。

佐々木敦 Atsushi Sasaki
撮影=新津保建秀
1964年生まれ。思考家/批評家/文筆家。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。芸術文化のさまざまな分野で活動。著書に『成熟の喪失』(朝日新書)、『「教授」と呼ばれた男』(筑摩書房)、『増補新版 ニッポンの思想』(ちくま文庫)、『増補・決定版 ニッポンの音楽』(扶桑社文庫)、『ニッポンの文学』(講談社現代新書)、『未知との遭遇【完全版】』(星海社新書)、『批評王』(工作舎)、『新しい小説のために』『それを小説と呼ぶ』(いずれも講談社)、『あなたは今、この文章を読んでいる。』(慶應義塾大学出版会)、小説『半睡』(書肆侃侃房)など多数。