カフェに
行く
-
第1部入場券+全編配信視聴権8,800円
-
第1部入場券+全編配信視聴権(中高生)5,500円
ネットで
見る
-
配信視聴3,850円
本イベントはゲンロン友の会会員限定でご参加いただけます。新規入会セットで2,000円値引きになるお得なキャンペーンを実施中ですので、まだ会員でない方はこちらからチケットをご購入ください。
【概要】
第15期総会は3月22日、昨年4月にオープンした「五反田JPビルディング」の1フロアを貸し切って、お昼から開催!
ゲンロン友の会総会とは、年に1度だけ行われる会員限定の大きな集会です。第15期で14回目を迎えます(第3期は未開催)。
トークありパフォーマンスあり展示あり会員の出店あり、ゲンロンの媒体でお馴染みの方が多数集結する、文字どおりのお祭りです。オンラインでも視聴できますので、ぜひいちどご参加ください。
第15期総会について詳しくはこちら!
※過去の総会について詳しくはこちらのページをご覧ください。
今回もプログラムは昼と夜の2部構成!
第1部(昼の部)は24年4月に開業した「五反田JPビルディング」の1フロアを貸し切って行われます!
豪華ゲストによるトークはもちろんのこと、例年好評をいただいている「ゲンロン・シラスコミュニティマーケット」をはじめ、こども教室やトレーディングカードといった、ご来場いただいた皆様同士の「雑談」を軸にパワーアップして開催します。
第2部(夜の部)は、ゲンロンカフェとシラススタジオ、ゲンロンオフィスの3会場!
「来場チケット」「配信チケット」共に、生配信終了後はアーカイブのご視聴も可能です。
総会の詳細についてはwebゲンロンの総会特集記事をご参照ください。
【配信プログラム】
第1部
12:00〜20:00/CITY HALL & GALLERY GOTANDA(五反田JPビル3階)
●開会の挨拶(ゲンロン代表 上田洋子)
・メインホール
●夏野剛×茂木健一郎×東浩紀
「雑談復活──経営と脳と哲学」
●小泉悠×松下隆志×上田洋子
「ソローキンとICBM──帝国復活」
・ギャラリー
●山内萌×植田将暉
「人文ウォッチ特別篇──オフレコ復活」
●河野咲子×天沢時生×伏見瞬
【ゴゴゴ会総会篇】
「なぜ働いているのにSFが書けるのか──タイムトラベル復活」
【パフォーマンス】
●堀内大助
「マジックショー──堀内復活」
●玉田玉山
「講談復活」
●吉田雅史
「『アンビバレント・ヒップホップ』刊行記念パフォーマンス──MA$A$HI復活」
●閉会の挨拶(ゲンロン創業者 東浩紀)
第2部
21:00〜28:00/ゲンロンカフェ、シラススタジオ、ゲンロンオフィス
【ゲンロンカフェ】
●田中宏和・西田亮介・桂大介・東浩紀
「五反田から世界を変える──友の会プレゼン祭り」
【シラススタジオ】
●さやわか×大井昌和×濱田轟天 司会=とらじろう
「ひらめきは五反田からやってくる」
●シラサーと語ろう!
出演:大槻香奈、速水健朗、綿野恵太
※夏野剛×茂木健一郎×東浩紀「雑談復活──経営と脳と哲学」および、小泉悠×松下隆志×上田洋子「ソローキンとICBM──帝国復活」は非会員でもシラスにて個別購入可能です(各2,420円)。
総会の配信チケットとはアーカイブ期間や金額が異なりますのでご了承ください。
配信されないプログラムも多数ございます。詳細はwebゲンロンをご覧ください。
https://webgenron.com/articles/sokai15

朝吹真理子

弓指寛治 Kanji Yumisashi
「自死」や「慰霊」をテーマに創作を続ける画家。大学院修了後、学生時代の友人と名古屋で映像制作会社を起業。2013年に代表取締役を辞任し上京、作家活動を開始した。ゲンロンカオス*ラウンジ新芸術校の第一期生として学んでいた2015年に、交通事故後で心身のバランスを崩していた母親が自死。出棺前に「金環を持った鳥のモチーフ」が浮かび、以後制作される多くの作品で繰り返し登場する彼の表現の核となっている。2018年には、約30年前に自死したアイドルをテーマにした《Oの慰霊》が第21回岡本太郎現代芸術賞で敏子賞を受ける。同年に同作の続編的な位置付けの展覧会「四月の人魚」が開催され大きく話題を集めた。 【撮影:小澤和哉】

夏野剛 Takeshi Natsuno
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授 / 株式会社KADOKAWA 代表執行役社長 / 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長
早稲田大学政治経済学部卒、東京ガス入社。ペンシルバニア大学経営大学院(ウォートンスクール)卒。ベンチャー企業副社長を経て、NTTドコモへ。「iモード」「おサイフケータイ」などの多くのサービスを立ち上げ、ドコモ執行役員を務めた。現在は近畿大学の特別招聘教授、情報学研究所長のほか、株式会社KADOKAWA代表執行役社長、株式会社ドワンゴ代表取締役社長、そして、トランスコスモス、グリー、U-NEXT HOLDINGS、日本オラクルの社外取締役を兼任。このほか経済産業省の未踏IT人材発掘・育成事業の統括プロジェクトマネージャー、内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム共同会長なども務める。

茂木健一郎 Kenichiro Mogi
脳科学者、作家、ブロードキャスター。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。1962年10月20日東京生まれ。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て現職。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードとして脳と心の関係を研究。2005年、『脳と仮想』で、第四回小林秀雄賞を受賞。2009年、『今、ここからすべての場所へ』で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。IKIGAIをテーマにした英語の著書が、31カ国、29言語で翻訳出版される。

小泉悠 Yu Koizumi
東京大学先端科学技術研究センター准教授。専門はロシアの軍事・安全保障政策。早稲田大学大学院政治学研究科(修士課程)修了後、民間企業勤務、外務省国際情報統括官組織専門分析員、ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、公益財団法人未来工学研究所研究員などを経て現職。主著に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版)、『現代ロシアの軍事戦略』、『ウクライナ戦争』(ともにちくま新書)、『終わらない戦争』(文春新書)などがある。『「帝国」ロシアの地政学』が第41回サントリー学芸賞を受賞。

松下隆志 Takashi Matsushita

石戸諭 Satoru Ishido
1984年、東京都生まれ。ノンフィクションライター。立命館大学法学部卒業。2006年、毎日新聞社に入社。2016年、BuzzFeed Japanに移籍。2018年、独立してフリーランスのライターに。2020年、「ニューズウィーク日本版」の特集「百田尚樹現象」で第26回編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞作品賞、2021年、「文藝春秋」掲載のレポート「『自粛警察』の正体」で第1回PEPジャーナリズム大賞を受賞。週刊誌から文芸誌、インターネットまで多彩なメディアヘの寄稿に加え、テレビ出演など幅広く活躍中。著書に、『リスクと生きる、死者と生きる』(亜紀書房)、『ルポ 百田尚樹現象 愛国ポピュリズムの現在地』(小学館)、『ニュースの未来』(光文社新書)、『視えない線を歩く』(講談社)、『東京ルポルタージュ』(毎日新聞出版)。

小松理虔 Riken Komatsu
撮影=鈴木禎司
1979年いわき市小名浜生まれ。ローカルアクティビスト。いわき市小名浜でオルタナティブスペース「UDOK.」を主宰しつつ、いわき海洋調べ隊「うみラボ」では、有志とともに定期的に福島第一原発沖の海洋調査を開催。そのほか、フリーランスの立場で地域の食や医療、福祉など、さまざまな分野の企画や情報発信に携わる。共著本に『常磐線中心主義 ジョーバンセントリズム』(河出書房新社)、『ローカルメディアの仕事術』(学芸出版社)ほか。初の単行本著書である『新復興論』(ゲンロン)が第18回大佛次郎論壇賞を受賞。2019年9月より『ゲンロンβ』にて「当事者から共事者へ」を連載中。

山内萌 Moe Yamauchi
1992年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。同大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(学術)。単著「『性教育』としてのティーン雑誌──1980年代の『ポップティーン』における性特集の分析」『メディア研究』104号(2024)、「性的自撮りにみる「見せる主体」としての女性」『現代風俗学研究』20号(2020)。共著『メディアと若者文化』(新泉社)。

河野咲子 Sakiko Kawano
作家・文筆家。小説「水溶性のダンス」にて第5回ゲンロンSF新人賞を受賞、同作はゲンロンSF文庫より刊行。SFの他、幻想怪奇小説、オペラ戯曲、テクスト批評などを執筆する。朗読出演、トーク企画配信、展覧会協力など幅広く活動。旅の批評誌『LOCUST』編集部員。日本SF作家クラブ会員。

天沢時生 Tokio Amasawa

伏見瞬 Shun Fushimi
東京生まれ。批評家/ライター。音楽をはじめ、表現文化全般に関する執筆を行いながら、旅行誌を擬態する批評誌『LOCUST』の編集長を2018年より務める。「ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾」第3期 東浩紀審査員特別賞。2021年12月に初の単著『スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック』を刊行。

田中宏和
1969年京都市木屋町生まれ。タナカヒロカズ運動発起人の「ほぼ幹事」。ブランド・クリエイティブ・ディレクター。大手広告代理店を経て2024年に独立、タナカヒロカズ株式会社を起業し、代表取締役社長兼CEOを務める。International Same Name Association(国際同姓同名連盟)共同設立者。渋谷のラジオ・プロデューサー兼パーソナリティ。東北ユースオーケストラ監事/事務局長。近著に『全員タナカヒロカズ』(新潮社)、他著書に『響け、希望の音 東北ユースオーケストラからつながる未来』(フレーベル館)、共著『田中宏和さん』(リーダーズノート)、編著『くらしのこよみ 七十二の季節と旬をたのしむ歳時記』(平凡社)など。

西田亮介 Ryosuke Nishida
1983年京都生まれ。日本大学危機管理学部教授/東京科学大学リベラルアーツ研究教育院特任教授。博士(政策・メディア)。慶應義塾大学総合政策学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同政策・メディア研究科助教(研究奨励Ⅱ)、(独)中小企業基盤整備機構経営支援情報センターリサーチャー、立命館大学大学院特別招聘准教授、東京工業大学准教授等を経て、2024年4月日本大学危機管理学部に着任。現在に至る。専門は公共政策の社会学。
著書に『ネット選挙』(2013年)『情報武装する政治』(2018年)、『新プロパガンダ論』(2021年、辻田真佐憲との共著)『17歳からの民主主義とメディアの授業』(2022年)、『日本再生の道』(2025年、石丸伸二との共著)、『エモさと報道』(2025年)など多数。

桂大介 Daisuke Katsura

さやわか Sayawaka
1974年生まれ。ライター、物語評論家、マンガ原作者。〈ゲンロン ひらめき☆マンガ教室〉主任講師。著書に『僕たちのゲーム史』、『文学の読み方』(いずれも星海社新書)、『キャラの思考法』、『世界を物語として生きるために』(いずれも青土社)、『名探偵コナンと平成』(コア新書)、『RPGのつくりかた:橋野桂と『メタファー:リファンタジオ』』(筑摩書房)、『ゲーム雑誌ガイドブック』(三才ブックス)など。編著に『マンガ家になる!』(ゲンロン、西島大介との共編)、マンガ原作に『キューティーミューティー』、『永守くんが一途すぎて困る。』(いずれもLINEコミックス、作画・ふみふみこ)がある。「コミックブリッジ」で『ヘルマンさんかく語りき』(作画:倉田三ノ路)を連載中。

大井昌和 Masakazu Ooi
第三回電撃ゲームコミック大賞銀賞
月刊電撃コミックガオ!にて『ひまわり幼稚園物語あいこでしょ』でデビュー。
主な作品は『ちぃちゃんのおしながき』『おくさん』『明日葉さんちのムコ暮らし』『ヒメコウカン』など。

濱田轟天 Gouten Hamada
1976年生まれ。東京都出身。2000年ちばてつや賞(一般部門)入賞。 職業漫画家を目指すも経験が足りず挫折。様々な職種を経験し、2009年からSNS等で漫画を発表し始める。 2021年持ち込みを再開。2022年『平和の国の島崎へ』で漫画原作者デビュー。2024年9月から別冊ヤングチャンピオン誌で『ウミガミ〜絶島のジェノサイド〜』連載開始。2025年1月からマンガワンで『ミハルの戦場』連載開始。2025年2月現在3本の連載でネーム原作を担当している。2024年マンガ大賞4位。第8回さいとう・たかを賞受賞。趣味はサバゲと怪談鑑賞。

大槻香奈 Kana Otsuki
1984年、京都出身の美術作家。嵯峨美術大学客員教授。2007年より活動を開始。主に少女モチーフの絵画作品を中心に、日本的感受性や空虚さを「うつわ」的に捉え、現代日本の情景や精神性を表現している。イラストレーターとしても書籍の装幀やCDジャケット等に数多く作品を提供。作品集に「その赤色は少女の瞳」(河出書房新社)、「ゆめの傷口」(アトリエサード)。2021年に日本の精神性を探る「日本現代うつわ論1」(ゆめしか出版)を企画し、以降毎年1冊ずつシリーズ刊行&ディレクションを担当する。2024年には芸術活動の実験の場として半オープンスペース「ゆめしか家」を企画し、ワークショップや展覧会、お茶会等のイベントを行う。

速水健朗 Kenro Hayamizu
フリーランス編集者・ライター。1973年生。主な分野は、文化全般、本や都市、メディア史など。近著『1973年に生まれて 団塊ジュニア世代の半世紀』ほか、『ケータイ小説的。——“再ヤンキー化”時代の少女たち』(原書房)、『ラーメンと愛国』(講談社現代新書)、『1995年』(ちくま新書)、『フード左翼とフード右翼』(朝日新書)、『東京β』(筑摩書房)、『東京どこに住む?』(朝日新書)など。
ポッドキャスト「これはニュースではない」配信中。
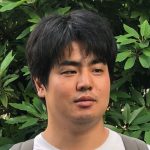
綿野恵太 Keita Watano
1988年生まれ。批評家。著書に『増補改訂版「差別はいけない」とみんないうけれど。』(朝日文庫)、『みんな政治でバカになる』(晶文社)、『「逆張り」の研究』(筑摩書房)。

東浩紀 Hiroki Azuma
1971年東京生まれ。批評家・作家。ZEN大学教授。博士(学術)。株式会社ゲンロン創業者。著書に『存在論的、郵便的』(第21回サントリー学芸賞)、『動物化するポストモダン』、『クォンタム・ファミリーズ』(第23回三島由紀夫賞)、『一般意志2.0』、『弱いつながり』(紀伊國屋じんぶん大賞2015)、『観光客の哲学』(第71回毎日出版文化賞)、『ゲンロン戦記』、『訂正可能性の哲学』、『訂正する力』、『平和と愚かさ』など。

上田洋子 Yoko Ueda
撮影=Gottingham
1974年生まれ。ロシア文学者、ロシア語通訳・翻訳者。博士(文学)。ゲンロン代表。早稲田大学非常勤講師。2023年度日本ロシア文学会大賞受賞。著書に『未完の万博』(共著、ゲンロン、2025)、『ロシア宇宙主義』(共訳、河出書房新社、2024)、『プッシー・ライオットの革命』(監修、DU BOOKS、2018)、『歌舞伎と革命ロシア』(編著、森話社、2017)、『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』(調査・監修、ゲンロン、2013)、『瞳孔の中 クルジジャノフスキイ作品集』(共訳、松籟社、2012)など。展示企画に「メイエルホリドの演劇と生涯:没後70年・復権55年」展(早稲田大学演劇博物館、2010)など。

植田将暉 Masaki Ueta
1999年、香川県生まれ。早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程。専門は憲法学。おもな著作に、「21世紀の「自然の権利」と大地の人類学」(『文化人類学研究』25巻)、『いま批評は存在できるのか』(共著、ゲンロン)ゲンロンでは編集と企画、ウォッチなどを担当。メディア研究者の山内萌とYouTube番組「今週の人文ウォッチ」を好評配信中!

吉田とらじろう Torajirou Yoshida
マンガ批評家。東京農業大学大学院博士後期課程(林学)在籍中。ゲンロン ひらめき☆マンガ教室を受講後、同教室の運営スタッフになる。同人活動として批評雑誌「ワタツミ」を定期的に発刊。文筆業のほかインタビューや配信イベントでの司会なども行う。
カフェに
行く
-
第1部入場券+全編配信視聴権8,800円
-
第1部入場券+全編配信視聴権(中高生)5,500円
ゲンロン友の会について詳しくはこちら
ネットで
見る
-
配信視聴3,850円
- 放送開始
- 2025/03/22 12:00
- 公開終了
- 2025/05/26 23:59


